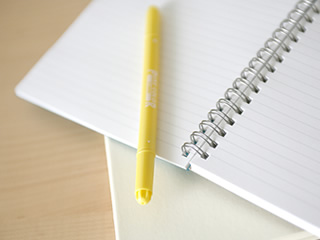|
2025/9/15
|
|
ハッピーマンデー |
|
|
本日は敬老の日でしたが、 月曜日に祝日が重なることが多いため、 年間スケジュールの都合上、 塾は平常通りの授業を行いました。
先日、講師たちと「月曜日は祝日が多いよね」という話になりました。 そのとき、私が 「ハッピーマンデー制度は我々にはちょっときついよね。」 と口にすると… 若い講師たちは揃って「???」 「ハッピーマンデー制度ってなんですか?」と、きょとんとした反応。 私がふざけて、適当に名前をつけたと思ったようです。
そうか、 彼らにとってはこれが当たり前。 そもそも制度ができる前のカレンダーを知らない世代なんですね。
三連休を作りやすくすることを目的としたこの制度は 2000年から 「成人の日」 1月15日→1月第2月曜日 「体育の日(現・スポーツの日)」10月10日→10月第2月曜日 2003年から 「海の日」 7月20日→7月第3月曜日 「敬老の日」9月15日→9月第3月曜日 に変更、実施されています。
こうした話題に触れるたび、 教育の現場にいると特に感じるのが、 世代によって「当たり前」がまったく異なるということ。
制度の変化、常識の変化、言葉の変化・・・。 生徒たちと接していても、 「えっ、そんなの知らないの?」と 驚かされることが日々あります。 でもそれは「知らない」ではなく、 「最初から存在しなかった」だけのこと。 私たち大人が「当たり前」だと思っていることが、 子どもたちにとっては「未知の世界」であることも少なくありません。
このような違いを感じたとき、 教える側が心がけたいのは、 「昔はこうだった」と押しつけるのではなく、 今の子たちにも伝わるように工夫して話すこと。 ただ知識を伝えるだけでなく、背景や理由も一緒に。 それが、世代を超えた理解につながるのではないかと思います。
|
|
| |