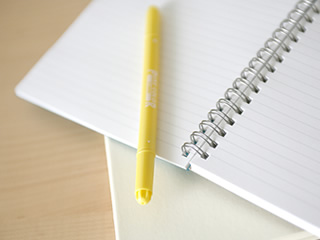|
2025/9/20
|
|
初めて食べた人もすごいけど・・・ |
|
|
以前、 「『かに』とか『納豆』とか、初めて食べた人ってすごい」 という話を書きました。(こちらのブログ) 考えてみたら、 初めて食べた人もすごいけど、 死者が出たり、 具合が悪くなったりしてる食べ物を あきらめず食べようとした人たちもすごいですね。 例えば 「ふぐ」。 今のような検査技術もない時代に、 どうやって毒のある部位を避けて食べる方法を見つけたのか。 それ以前に、 「何人食べて、何人倒れたんだろう……」なんて想像すると、 ちょっとゾッとします。 それでもなお、 「これはうまい!」 「安全に食べられる方法があるはずだ!」と 挑み続けた人たちがいたからこそ、 いま私たちは安心してふぐを味わえるわけです。 食の歴史って、 命がけの実験の積み重ねでもあるんですね。 同じように、 もう一つ驚かされるのが「こんにゃく」。 見た目はちょっとゴツゴツした芋。 しかも、そのまま食べると毒があって、 昔の人も実際に中毒を起こしていたと言われています。 それなのに、 何度もすりつぶして、水にさらして、灰汁で固めて…と、 とんでもない手間をかけてまで、 「食べられる形」に仕上げたんです。 なぜそこまでして食べようと思ったのかなあ。 おいしいのか?と聞かれると、 これまた主張が強いわけでもないし・・・。 だけど、今では日本の食卓に欠かせない存在ですよね。 「食べたい」という情熱と、 「食べられる形にするには?」という探究心の融合。 まさに、食文化の深さを感じます。 こうして考えてみると、 「食べられそうにないものを、どうにかして食べようとする」 そんな人間の執念と探究心には、 ただただ驚かされます。 安全も保証されていない時代に、 命のリスクを背負いながら、 「おいしさ」や「食べる方法」を追い求めてきた先人たち。 私たちが当たり前に食べているものの裏には、 そんな命がけの挑戦があったのかもしれません。 「食べる」という行為一つとっても、 人間の知恵と情熱の積み重ねであることを思い知らされますね。 |
|
| |